 (2009年各種案内)
(2009年各種案内)
「もう、怒らない」〜そう言うあなたが一番偉そうよ(2009年12月)
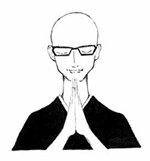
一年前、父の通夜が営まれた日に、「ああいう偉そうな奴は大嫌いだ。」と言った私に、妹は「そういうお兄ちゃんが一番偉そうよ。」といみじくも言葉を返したことがあります。うつ病の回復期に一時的に謙虚になっていた私は傲慢な性格を取り戻し、更に増長し傲岸不遜になっていました。自分のことは棚に上げて、他人のちょっとした所作に怒り、なじっていました。人格が壊れていると言っても良かったでしょう。自分でもそのことに気づいて反省もするのですが、すぐに忘れて同じことの繰り返しです。
11月22日、例によって四条のジュンク堂に立ち寄り、1階で本を10冊ほど選びました。その中に、小池龍之介の「もう、怒らない」が含まれていました。新聞広告で若い僧侶が書いた本ということだけは知っていましたが、単純に書名に惹かれて買っただけでした。帰って読んでみると、1978年生まれで東大教養学部卒のお坊さんが書いた本で、三大煩悩である「欲望」「怒り」「迷い」を生み出す心の仕組みを理解し、怒って自分を痛みつけることからも、怒って他人に被害を与えることからも卒業しましょう、と序文に書いてありますが、実は第1章から突っ込みどころ満載です。“それはちゃうやろ”と突っ込みながら読んでいくと、決して目新しいことではないけれども、“まあそうやな”と思われる部分が出てきます。
「世間的に怒りについては、我慢して抑圧するというやり方と発散してぶつけるというやり方があるが、どちらも誤りで第三の道を選びましょう。それは怒りの感情を客観視して穏やかに受け入れるという道です。見つめている自らの心と見られている怒りとが切り離されて、怒りが鎮静します。」という部分を読むと、「私は自分を客観的に見ることができる。あなたとは違う。」とキレた福田康夫元首相を思い出しますが、自分の怒りを客観視するというのは、正しい態度であるように考えられます。“自分の煩悩は好き、他人の煩悩は大嫌い”、“心は普通やありきたりが大嫌い”の項目も納得できます。
ベッドでこの本を途中まで読みながら眠ってしまい、翌11月23日よみがえる勤労感謝の日(「蘇える金狼」より by
Koishi)の夜明け前に父が夢枕に立ちました。私が小学生の頃までのめちゃめちゃ怖かった父と、中学生の頃からの怒らなくなった父とが両方出てきました。彼我の立場を尊重しながら、“個人”の本質に接するのが本来の生き方である、という彼の理念を夢の中で思い出しました。目を覚ました私は、“もう、怒らない”とつぶやきました。今までの私の人格は10点満点で2点ぐらいでしたが、12月1日の今日まで1週間も怒っていないので3点になりました。今後は5年で1点ずつ上げて、最終的に人格9点ぐらいになり、“優しいおじいちゃん”と呼ばれて死ぬ予定です。
アイリッシュセター part.3(犬の賢さ)(2009年11月)

飼い主の言うことを忠実に守るのが賢い犬だとしたら、シャルルはあまり点数が良くありません。わがままで、自分のやりたいことをする犬だからです。でも、犬舎の窓の開け閉めによる冷暖房の調節、扇風機のオンオフは自分で出来るし、みかんを丸ごとやると実の部分だけ上手に食べます。賢い!
シャルルのことを3番目の子供と思っているので、出来の悪い子のことも賢く思ってしまう、単なる親バカですね。
いきものがかり「じょいふる」/「エビバデポッキー!」(2009年10月)

2009年10月から江崎グリコのポッキーCM「エビバデポッキー篇」は忽那汐里に加えて、益若つばさ、IMALUの3パターンが放映されていますが、第50代ポッキープリンセスである忽那汐里バージョンが断然ハジケ(過ぎ)ています。オフィス街で、秋葉原で、国家議事堂前で、魚市場で、ギャルママと、コスプレメイドと、ガールズバンドと踊りまくっています。
いきものがかりの「じょいふる」が「エビバデポッキー篇」のCMソングですが、2009年度NHK全国学校音楽コンクール中学の部課題曲「YELL」の両A面カップリング曲でもあります。それぞれの道を選んで、未来へと飛び立っていく友と自分に対する「YELL」を松任谷正隆のアレンジで情感溢れるバラードに仕上げ、「じょいふる」を弾けるアップテンポで歌ういきものがかりは今ノリノリですね。

ポッキーのCMはその時代を代表するアイドルが起用され、松田聖子、本田美奈子などの作品やまだ10代の田中麗奈と妻夫木聡が共演する作品などをYouTubeで見ることが出来ます。
 記憶に新しいところでは、2006年にポッキー極細のイメージキャラクターとして新垣結衣が登場しました。“友達から「手を肩から上にあげない」と言われるほど、普段機敏な動きはしなく、ポッキーCMでのダンスは自分の体じゃないみたいで気持ち悪かった。”とインタビューで語っていたそうですが、「ガッキーのポッキーダンス」は技術的にはともかく、その天衣無縫な笑顔とキャラクターで大成功でした。他の人がやったら、ぶりっ子と言われて嫌みになるかも知れないところです。 記憶に新しいところでは、2006年にポッキー極細のイメージキャラクターとして新垣結衣が登場しました。“友達から「手を肩から上にあげない」と言われるほど、普段機敏な動きはしなく、ポッキーCMでのダンスは自分の体じゃないみたいで気持ち悪かった。”とインタビューで語っていたそうですが、「ガッキーのポッキーダンス」は技術的にはともかく、その天衣無縫な笑顔とキャラクターで大成功でした。他の人がやったら、ぶりっ子と言われて嫌みになるかも知れないところです。
京都の人の中華思想(2009年9月)
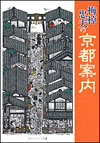
私は尼崎生まれですが、物心が付いてから高校を卒業するまで福知山で育ちました。京都に16年住みましたが、その後福知山でまた15年暮らしているので、立派な田舎者です。
 2009年8月7日(金)の「ちちんぷいぷい」で衆議院京都5区の選挙運動を西靖が取材した映像が流れた際、玉木正之が、“こんな田舎が京都とは思えない。”というニュアンスのことを言っていましたが、“地元の人も、この辺が京都とは思っていない。行政区分が京都府なだけやろ。あほちゃうか。”とテレビに向かってつぶやきました。京都に生まれ育った人が垣間見せる中華思想には辟易します。梅棹忠夫ほどの人でも、現在京都に住んでいても他の場所から移って来た人は他郷の人と一括りで、“生粋の京都市民であるところの私と他郷の人との間には深い溝ないしは堀があって、お互いを隔てている。”ときます。あんた、京都なんて東京と比べたら勿論、大阪と比べても随分田舎でっせ。それに、あなたさまの祖先を辿ると、京都市でも日本でもないところに暮らしておられたんとちゃいまっか。
2009年8月7日(金)の「ちちんぷいぷい」で衆議院京都5区の選挙運動を西靖が取材した映像が流れた際、玉木正之が、“こんな田舎が京都とは思えない。”というニュアンスのことを言っていましたが、“地元の人も、この辺が京都とは思っていない。行政区分が京都府なだけやろ。あほちゃうか。”とテレビに向かってつぶやきました。京都に生まれ育った人が垣間見せる中華思想には辟易します。梅棹忠夫ほどの人でも、現在京都に住んでいても他の場所から移って来た人は他郷の人と一括りで、“生粋の京都市民であるところの私と他郷の人との間には深い溝ないしは堀があって、お互いを隔てている。”ときます。あんた、京都なんて東京と比べたら勿論、大阪と比べても随分田舎でっせ。それに、あなたさまの祖先を辿ると、京都市でも日本でもないところに暮らしておられたんとちゃいまっか。
もっとも、私が贔屓にしていた景山民夫は「あのころ君はバカだった」で“品川と横浜ナンバー以外は代官山に来るなッ!!”と叫んでいたし、「食わせろ!!」では、“上越新幹線と東北自動車道を爆破して、田舎者が帰省先から東京に戻って来られないようにしてやる。”と悪態をついていたので、中華思想は京都人に限りません。却って、余所者に対する“排除の論理”は田舎の方がもっとずっと強いのかも知れません。
本屋さんpart.3(三月書房と田毎のたぬき)(2009年8月)

三月書房は知る人ぞ知るカルト書店で、そのホームページには「京都・寺町二条の地べたの書店です。古本屋ではありません、新本屋です。」とあります。はてなキーワードによると、「品揃えが個性的で、こだわりをもって集められた内容の濃い本がそれほど広くない(はっきり言って狭い)店内にぎっしりと詰まっている。思想・芸術・文学・詩歌・サブカルチャー・マイナーな漫画(例えばガロ系)などのジャンルに強い。」2009年5月号をもって残念ながら休刊となった「エスクァイア日本版」の“京都だけが知っている”特集で、武田好史氏は「その小さな店舗がまだ見ぬ亜空間の入り口になっている。時計の針が逆へ回り、人生の変更を余儀なくされる絡繰、そんなパサージュが京都にはそこかしこに用意されている。一休も世阿弥も千利休も本阿弥光悦も若沖もいた京都だが、こうして一軒の書店のドアからはアンドレ・ブルトンもそしてナジャでさえパリのラファイエット通りからやってこれるのだ。」と語っています。
戦後すぐに三月書房を始めた宍戸恭一氏によると、「本は魂を持っている。」「本ていうのは生活の糧であり、生き物ですからね、魂を持ってる。一冊だけポツンとあったんではダメです。関連させて初めて生きてくる。その点、新刊の書店いうのはほとんど参考にならん。本が死んでるんですよね、疲れるばっかりで。大きなところはポツンポツンと置いとるでしょ。機械的なジャンル別やとか、それやられたんじゃ、どうしようもないんです。関連させて初めて生きてくる。」三月書房に置かれた本たちは幸せ者ですね。

さて、三月書房で知的好奇心を満たした後は、お腹を満たさなければなりません。となると、三条寺町の田毎のたぬきです。京都が実家のイラストレーターみうらじゅんは、京阪神エルマガジン社の「京都の迷い方」で田毎のたぬきうどんを絶賛していますが、私はたぬきそば派です。京たぬきはきざんだ油揚げの上から葛餡をかけたもので、ねぎと生姜と七味のバランスが肝です。
まだ結婚する前に妻と「三嶋亭」のすき焼を食べに行って、その量の少なさに満足できず、追加の肉を頼むのも癪で、其の足で田毎へ寄って、天ぷらそばを食べたのが思い出されます。
巴里の女〜「禁じられた遊び」と「望郷」から(2009年7月)
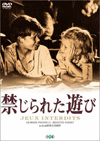
文藝春秋SPECIAL“映画が人生を教えてくれた”において、弁護士の堀田力氏は「禁じられた遊び」(ルネ・クレマン監督)について、「まだ戦争の痛みが消えていない昭和20年代、高校の授業を抜け出して潜り込んでいた京都・祇園の映画館で、男は人に涙を見せてはならないという古い社会の規範が色濃く残っていたので、涙を抑えるのに苦労した。」と述べています。また、角川文庫「外国映画ベスト200」には、撮影監督の仙元誠三氏の「中学時代に社会実習の団体鑑賞で涙を流し、劇場の明かりがパッとついたとき、小さいながらに女の子に涙顔を見せたくないと思ったことが今でも強く心に残っている。」という堀田氏とよく似たコメントが載っています。長老映画評論家の双葉十三郎は「クレマン監督は、単なる反戦映画ではなく、生と死の映画詩にまで作品を高めた。」と評価しています。
 ところが、私はこの映画にもっとクールな印象を持ちました。きっと、上記の三人と違い、私が“戦争を知らない子供たち”であるのが、大きな要因であるとは思います。そこで、淀川長治の一行解説です。「パリの女の子が田舎の男の子をアゴで使った十字架遊び。」素晴らしい!「パリの女というものは、こんな小さいときから男をあしらう術を知っているんだ。怖いなあ。このあたりが、この映画のほんとうに面白いところですね。」
ところが、私はこの映画にもっとクールな印象を持ちました。きっと、上記の三人と違い、私が“戦争を知らない子供たち”であるのが、大きな要因であるとは思います。そこで、淀川長治の一行解説です。「パリの女の子が田舎の男の子をアゴで使った十字架遊び。」素晴らしい!「パリの女というものは、こんな小さいときから男をあしらう術を知っているんだ。怖いなあ。このあたりが、この映画のほんとうに面白いところですね。」
パリの女と言えば、「望郷」(ジュリアン・デュヴィヴィエ監督)のギャビー(ミレーユ・バラン)です。異郷の地アルジェリアのカスバで、ペペ・ル・モコ(ジャン・ギャバン)はこのパリジェンヌに一目惚れするのですが、彼女自身に胸ときめかせると同時に、ギャビーを通してパリへの望郷(homesickness/nostalgia)の念にかられます。本当にジャン・ギャバンが格好良すぎです。アラン・ドロンの紹介をするときに必ず出てくるフレーズが、「フランスではルックスよりも存在感を重く見る。ジャン・ギャバンからジャン・ポール・ベルモンドに繋がるジャガイモ顔だが、何とも言えぬ存在感がある俳優の方がドロンより人気だ。」というものですが、この作品のジャン・ギャバンたるや存在感はもとより、ルックスも最高に良いです。スリマン刑事の憎たらしさもよろしい。
自慢はやめて!(2009年6月)
妻が、長男の学校行事から帰って来て、「同級生のお母さんがうちのホームページのことを話していたけれども、あなた自慢話をしているのね。」とのたまいました。妻はアンチエイジングラボページを除いて当ホームページをあまり見てない(興味ない)のですね。私は、普段他のブログやホームページを見ては、「ビジネスの宣伝か、自慢か、他人の悪口ばかりだね。臆病な人は自慢も悪口も書けなくて、当たり障りの無い本当にどうでも良いことしか載せてない場合もあるけど。」と言っている割には、このページがたいしたこと無いのを自覚しています。
結局、自分や自分の周囲について悪いことを書かないので、結果として自慢話に感じられるのでしょう。母が、「あなたの良いところは煙草を吸わないことぐらいね。」と言ったことがありますが、周知のように私には良いところは少なく、欠点は山ほどあります。子どもたちにも、死ぬほど直して欲しい悪いところがあります。妻は客観的に見ても、比較的そつがないほうですが。(ヨイショ!)
と言いながら、例によって改めるつもりも無く、人生を過ごしていきます。
「天井桟敷の人々」(2009年5月)
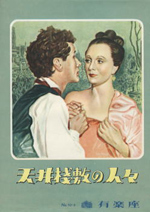
私の数多い弱点の一つに映画について詳しくないことが挙げられます。そこで、名作と呼ばれる映画を週に一作は観るという習慣を始めました。まず、母が3回映画館で観て、ラストシーンが最高という「第三の男」から新しい習慣はスタートしました。
そして、マルセル・カルネ監督の「天井桟敷の人々」です。この映画は1945年(昭和20年)3月9日にフランスで公開されたといいますから、終戦前ですね。当時パリはナチスドイツの占領下であったのにも拘らず、ニースで巨大セットを作り、3年3ヶ月と破格の制作費をかけて生まれたフランス映画の大傑作です。第二次世界大戦中の作品なのに戦争の陰は薄く、其処にあるのは“心臓が締め付けられるような男と女の恋の歓びと哀しみ”です。
純真無垢な無言劇の役者バチスト(ジャン=ルイ・バロー)と孤独な人生経験から打算的に振る舞う踊り子ガランス(アルレッティ)。不似合いと言える二人ですが、互いに惹かれ合います。恋愛の経験豊富なガランスは「恋なんて簡単よ。」とバチストに囁きますが、これほどまでに女性を愛したことが無いバチストはガランスを抱くことができません。ひとときも忘れることが出来ない相思相愛の二人なのに、別々の人生を歩んで行くことになります。
運命の再会を果たし、想い出の部屋でバチストとガランスはようやく結ばれます。カーニバルでパリが賑わう翌朝、バチストを深く愛する妻が息子とやってきます。それを見たガランスはピエール・ラスネールに夫モントレー伯爵が殺害されたことも知らずに旅立ちます。もはやガランスのことしか見えないバチストは大声で叫びながら彼女を追いかけますが、カーニバルの雑踏に邪魔され、二人はまた離れ離れになってしまいます。
この歳になっても、見終わって“胸きゅん”ものです。これからの二人の運命や如何に。「いやぁ、映画ってほんっとうにいいもんですね〜」「それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら‥‥ 」
モリミーとマキメpart.2(2009年4月)

3月7日、大丸の駐車場からいつものように四条通を歩いてジュンク堂に入ると、一番目立つところに森見登美彦の「恋文の技術」と万城目学の「プリンセス・トヨトミ」がありました。ある程度分厚い本ですが、内容はとても軽いので2冊ともすぐ読めました。
モリミーは相変わらず、スケールが小さい!(彼にとっては褒め言葉です。)「恋文の技術」では、意図的に過去の作品の登場人物を彷彿とさせて、へたれでほっこりしたモリミーワールド好きの読者の期待を裏切りません。鬱屈した男がコンプレックスとプライドと下心を混在させた手紙を書くのですが、森見氏の文学的素養に裏打ちされたユーモアが溢れています。今回のような力を抜いた作品も良いですが、次に出るらしい“次女”にも期待しております。

「プリンセス・トヨトミ」を読み始めて、学士会報(平成20年5月発行)の「万城目学の国会探訪」の中で、作品に国会を登場させる予定と語っていたのはこれのことだったのかとまず思いました。 彼は追手門学院小→清風南海中・高ですから、大阪はまさに彼の地元です。「鴨川ホルモー」で“京都のオニ”、「鹿男あをによし」で“喋る奈良のシカ”を題材にファンタジーを描きましたが、まさに満を持して大阪を舞台とする「プリンセス・トヨトミ」を執筆したのでしょう。ただし、この作品は奇想天外でスケールはでかいけれども、何とも粗い部分が散見されます。会計検査院の3人は良いとして、とても重要な登場人物である真田幸一と大輔の親子、橋場茶子の描写は魅力的でなく、肝心な部分が不足し、書かなくても良い部分が冗長です。大輔がDIDであるのは、発想としては面白いけれども、作品に生かされていません。まあ、「鹿男あをによし」「鴨川ホルモー」に続いて、映像化されるのは確実でしょう。旭ゲーンズブールと茶子のキャスティングがポイントですね。
テニスpart.4(ラストマッチ)(2009年3月)

2008年7月に大阪靭テニスセンターで行われた関西ジュニアテニス選手権14歳以下男子ダブルスの準々決勝が長男のラストマッチになりました。仲良しの選手とペアを組み、灼熱の太陽の下で頑張りましたが、4-6、4-6で敗れました。もう1年間は14歳以下でやれるのですが、一区切りをつけました。

中学生や高校生になると、テニスに限らずスポーツを最優先に考える選手は毎日毎日練習しなければなりません。長男は小学生までのように週3回の練習もままなりませんし、プライオリティーのトップはテニスではありません。(走るのが好きなので、部活は陸上部ですし。)自分自身でも、テニスは大好きなのに、試合にはパッションを感じられなくなっていました。
テニスは生涯スポーツなので、大学入学後でも社会人になってからでもまた試合に出ることは可能です。既に大学のテニスサークルでもてるくらいにはなっているのではと私なんかは思いますが、(本当に誰に似たのか)彼は硬派なので関係ないようです。
人間の習慣(2009年2月)
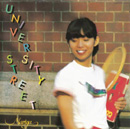
几帳面な人は言うまでもなく、ずぼらな人であっても、人間の生活は習慣に規定されます。仕事でも勉強でも趣味でも毎日していることを一日でも休むと気持ち悪いものです。しかしながら、何らかの契機でその習慣から遠ざかると、最初は苦しくても、時間が経てば結構平気になります。今までしていたことをしなくなるのが、新しい習慣になるからです。そうでなければ、人間は新しいことにチャレンジできませんし、失恋をして新しい恋を見つけることも出来ません。
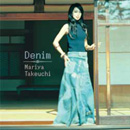
大学生の頃までは、時間なんていくらでもあると思っていたけど、最近はあっという間に一週間、一ヶ月、一年が過ぎていきます。少年チョット老い易く、青年マァマァ老い易く、壮年メッチャ老い易く、老年チョー老い易いと感じます。
“UNIVERSITY
STREET”で「バィビィ」と言っていた頃の竹内まりや(20代)は、“毎日がスペシャル”(40代)「誰もがみんなちょっとずつ年をとってゆくから 何でもない一日が実はすごく大切さ」とか、“人生の扉”(50代)「気がつけば五十路を越えた私がいる 信じられない速さで時は過ぎ去ると知ってしまったら どんな小さなことも覚えていたいと心が言ったよ」とかは思わなかったでしょう。
そして、“They say it’s lovely to be 40”から、まもなく“I feel it’s nice to be
50”となるのでありますが、ささやかでも幸せな気分に浸れる習慣を得たいものです。
Man is mortal(2009年1月)
Man is
mortal. 平成20年12月19日に父岡本利彦が亡くなりました。産婦人科医として生命の誕生、そして終焉に立ち会って来ましたが、父の死を看取るという行為にはやはり通常とは異なる感慨がありました。自宅で亡くなったため、死亡診断書は私が書きました。肝細胞癌を主たる死因と記載しましたが、癌とは無関係に穏やかに魂が現世から離れていった、まさに天寿を全うしたと考えています。
父は文章を書くのが好きであり、ややレトリックにしつこすぎるきらいはありましたが、比較的格調高いものでした。衒学的、皮相的な私の文章とは異なります。折々に綴られた文章を読み返し、父の人生を考えてみました。
父利彦は、昭和3年11月25日に福知山市で生まれました。惇明小学校時代は学校の行き帰りに本を読みながら歩く“勉強好きな少年”と呼ばれたそうですが、本人は『女学校の生徒と視線を合わせるのが恥ずかしかったから、本を読むふりをしていただけだ。』と言っておりました。
旧制の福知山中学校を経て、第三高等学校に入学しました。生命体としての誕生は福知山に於いてですが、『人間として生まれ育ったのは京都吉田の地であった。』と父は語っています。『自動他動を問わず、規則や指示で固めての管理を好む人が居れば、緩い縛りの中での自律を望む人も居る。何れも結構だが、個人の倫理観に訴えずに罰則で束縛するのは、避けるべきである。人が集まれば種々雑多な顔が見えるのは当然であり、寧ろ同色に染められた集団は不気味でさえある。彼我の立場を尊重しながら、“個人”の本質に接するのが本来の生き方である。自ら信ずるところに従った行為に対して、弁明は無用と心得る。』と福知山高校創立百周年記念式典で述べています。“弁明は無用”を貫いたので、時として“傲然たる満腔の自信家”と誤解されたこともありましたが、これこそ、父が三高で学んだ、終生変わることが無かった理念でありました。
大学は新制京都大学医学部と旧制大阪大学医学部の選択で、旧制阪大に進学しました。阪大医学部の進取の精神に富み、バイタリティ溢れる環境に身を置けたのは彼のキャリアにとってとても良かったのでしょう。
卒業後に産婦人科を選択し、ここ福知山の地で開業医になりました。私が高校生の頃、「田舎町で開業医になるより、大学に残った方が良かったのでは?」と聞いた時、父は『福知山の臨床医の方がずっと良い。』と断言しました。『時には激烈岩を噛む姿を見せて流れ来る流れ去る急流、時には深淵に臨んで悠然とたゆたう大河、その緩急と曲折の道程を顧みるとき、先達の喜びを我らが喜びとし、難局に直面しての見識と手法をその行動から学びとって生かさねばならない。人の心といい、社会の有り様といい、何を以て真となすのか。真実一路、ひたすら鈴振り追い求めても、彼は常に変わり身鋭く、スルリと逃げ去っていきます。我々医師たる者は、人の思惑も時代をも超越して、自分の都合のみで仕事に従事するのではなく、時には自らを傍らに置いても地域住民のために努める気構えが必要であり義務であると私は考えます。権利の主張は義務の遂行があって初めて信頼されるものとなり得ます。』と福知山医師会創立百周年記念式典で述べています。こんなものは建前だけだ、と批判されるかもしれませんが、少なくとも彼は真剣にそう信じていたと私は思います。
2003年から4年にかけて、私が重症うつ病に罹患し、太宰治の晩年の作品に出てくる廃人のような生活を送った時、父は私にこんな手紙を送ってくれました。『研究者は極端な場合、たとえ人格破綻者であっても一向に構わないが、臨床医は人間との個人的な係わり合いの中で仕事を為すものである。それぞれ個性を持った様々な人々と“容認”を前提とした関係を構築し、協力して疾病と闘うのが臨床医である。「子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず。」付和雷同することなく、主体性を持って人と仲良くする。自分自身の堅持は必要だが、まず和することが大切である。』私の個人的資質から、和することは極めて困難ですが、努力はしてみます。
晩年に『自分の人生はつきまくった人生だった。』と父利彦は語っていました。自ら天職と思える職業に巡り会うことができました。皆様方のお力添えで、幾らかの仕事を成し遂げることが出来ました。ゴルフという大好きな趣味にも出会えてシングルプレイヤーになれました。そして、母という最愛の人を伴侶とし、最後まで一緒に人生を送れました。出来ることならば、最後は読むことの出来無かった書物を紐解き、真実を見詰め続け、天国から私達家族を見守ってくれるように希望します。
|


